

1.はじめに
古来より、疾患を理解し、診断・治療を行うために病変の可視化が試みられてきたが、体表面に病変がある場合を除いて、侵襲性の高い外科的処置なしに病変を体表から視認するのは困難であった。1970年代にComputed Tomography(CT)や超音波診断装置、消化管内視鏡などの革新的な画像診断装置が次々と実用化されると非侵襲・低侵襲で病変が可視化され、疾患の診断精度が格段に向上すると共に、疾患の病態メカニズムの理解が進んだ。本稿では、日本発の光学医療機器である消化管内視鏡に焦点を当て、画像センサがどのように内視鏡技術を支えているか概説する。
2.消化管内視鏡と画像強調内視鏡
消化管内視鏡の原型は1950年に東京大学とOlympus社の協同研究で開発された胃カメラにある1)。当初は先端部のカメラと光源で胃内部の写真を撮影するもので、目視によるリアルタイム観察ができなかった。光ファイバの開発によって胃カメラはファイバスコープへと変容し、接眼部から胃内部を直接視認できるようになった。さらにCCD画像センサの小型化が進むと先端部にCCDカメラを内蔵したビデオスコープが開発され、消化管内腔の画像をリアルタイムに複数人で共有できるようになった。ビデオスコープ開発から約50年、消化管内視鏡は消化器癌の早期発見に必須の検査となり、現在では胃・十二指腸で年間50万件、大腸で20万件を超える検査が国内で行われている(図1)2)。
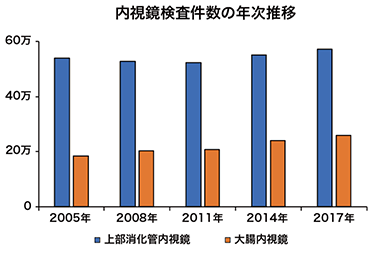
(政府統計:医療施設調査、一般病院の統計2))
消化管内腔が見えるようになると、粘膜表面の癌が肉眼で判別しにくいなど、通常の光学観察で病変特定が困難なケースが多く存在する事が分かってきた。そこで近年は早期癌や炎症を検出する新たな画像解析技術の研究開発が行われている。Olympus社のNarrow Band Imaging(NBI)や富士フイルム社のFlexible spectral Imaging Color Enhancement(FICE)など画像強調技術は臨床応用も順次進んでおり、この分野でも日本が世界をリードしている3)。
ここで言う画像強調とは、ヘモグロビンの吸収波長が周辺組織と異なることを利用し、血管の輪郭を強調して可視化する画像処理技術である4)。生体に光を照射すると、血液中の赤血球に多く含まれる色素ヘモグロビンが400 nm付近と520 nm付近の波長帯の光を強く吸収する(図2a)。一方、同じ波長でも血管の周辺組織を進む光は吸収されずに散乱して体表面に戻るため(図2b)、血管に当たった光とそうでない光とでヘモグロビンの吸収波長帯の明暗コントラストが大きくなる。NBIは青色と緑色の狭帯域光を照射し、血管で両者の光が吸収されることから血管の輪郭を強調する。FICEは白色光を照射し、粘膜からの散乱光スペクトル分析から、青色光や緑色光の吸収が強い血管の輪郭を描出する。照射光や画像取得法に違いはあるが、癌で早期から増成する血管を捉えて癌の早期発見を実現する画期的な画像技術である。さらに、光の特性として波長の短い青色光は表皮付近で散乱・吸収が生じ、波長の長い緑色光は青色光より深部まで到達する。このため青色光は浅い部分、緑色光は深い部分の血管の可視化に適する。今後は画像分析によって、血管の広がりだけでなく深さ方向まで、より詳細な走行を可視化できるようになると期待される。
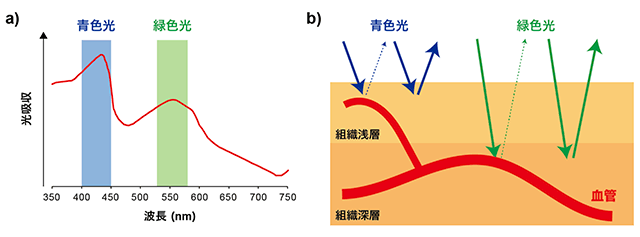
b) 血管と周辺組織における光の散乱・吸収
3.画像センサとカラー画像
内視鏡や画像強調観察には、光を検出する画像センサが必要不可欠である。画像センサでは受光素子の数が画素数として表現されるが、各受光素子のフォトダイオードが受光すると、光の強弱に応じた電荷を生じる(光電変換)。受光素子で変換・蓄積された電荷は、増幅器で電荷に応じた電圧値に変換されて信号出力される。固体撮像素子には電荷の伝送形式が異なるCCD(Charge Coupled Device:電荷結合素子)とCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor:相補型金属酸化膜半導体)がある。CCDセンサではフォトダイオードの電荷は伝送路をバケツリレーのように伝送・統合され、増幅器で電圧に変換される。一般にCCDセンサは高感度・低ノイズだが、常に全ての素子を稼働させるため電力消費が大きく、また高度な製造技術を要するため高価になる傾向がある。一方CMOSセンサは個々の画素がフォトダイオードとトランジスタを備え、画素ごとに信号を増幅して読み出すことで高速伝送を可能にする。CCDより安価で消費電力が小さく、高集積化によるオンチップデバイスなど小型化も進んでいる。以前はCCDに比べて高ノイズ・低感度とされてきたが、最近では低ノイズ・高感度化されている。初期には内視鏡先端部は主にCCDセンサが用いられたが、最近では高感度CMOSセンサを搭載した内視鏡も多く開発されている。
画像センサはさらにモノクローム(モノクロ)センサとカラーセンサに分けられる。モノクロセンサは被写体からの光量に応じて白から黒までの濃淡を2n階調(n: ビット数)で表すが、色情報は欠落する。一方カラーセンサは、受光素子にR、G、B三色のフィルタを搭載し、各受光素子がフィルタに対応する色を検出してカラー画像を取得する。光沢などのために明暗だけで表面情報を検出できない観察対象でも色に基づいた検出ができるが、フィルタ越しの検出で感度が低下し、受光素子を3色に割り振るため単色ごとの受光素子数が減少して解像度も低下する。モノクロセンサでもカラー画像取得は可能である。対象に青・緑・赤色の単色光を照射してモノクロ画像で撮像し、光量に対応する階調で各照射光に該当する擬似カラーを割り当てて合成すると、白色光で撮像したようにカラー画像を再構築できる。光源の切り替えや画像処理のため時間分解能は低下するが、高解像度のカラー画像を取得できる。
ここまで医療における画像技術の応用例として消化管内視鏡を紹介し、それを支える画像センサについて概説した。後半では画像センサで得られた画像の評価について、当研究室の研究成果の一部を紹介しつつ概説する。
次回に続く-
参考文献
- オリンパスグループ企業情報サイト(参照日: 2022年4月10日)
https://www.olympus.co.jp/technology/museum/endo/ - 政府統計:医療施設調査 平成20・23・26・29年 医療施設(静態・動態)調査
- 永尾 重昭.画像強調観察(Image-Enhanced Endoscopy)を用いた消化管腫瘍診療の最前線,日本内科学会雑誌. 2013; 102巻: 7号.
- 小田島慎也,藤代光弘,小池和彦.画像強調イメージングの特徴―NBI, FICE, i-scan―.
日本消化器内視鏡学会雑誌. 2010; 51巻: 9号.
【著者紹介】
納谷 友希(なや ゆうき)
徳島大学大学院医学研究科医科学専攻 生体防御医学分野
徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所 医光融合研究部門
■略歴
2017〜2021年 徳島大学理工学部 理工学科 情報光システムコース(光系)
2021年〜 徳島大学大学院医科学教育部 医学研究科 医科学専攻
理工学部から「医学と光技術を融合させた研究」に興味を持ち、徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所医光融合研究部門の髙成研究室で卒業研究を行う。現在も同研究室にて修論研究に従事している。
髙成 広起(たかなり ひろき)
徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所 医光融合研究部門 准教授
■略歴
2000年 名古屋大学医学部医学科 卒業
2011年 名古屋大学大学院医学系研究科 学位(医学)取得
2011〜2013年 University Medical Center Utrecht(オランダ) 博士研究員
2013〜2016年 大分大学医学部 病態生理学講座 助教
2016〜2019年 徳島大学病院 糖尿病対策センター 特任講師
2019〜2022年 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所 医光融合研究部門 特任講師
2022年〜 現職
6年間の臨床医としての経験を経て基礎研究へ転身。主に細胞や生体の生理機能を視覚的に捉えるバイオイメージングの研究を行う。2019年から徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所医光融合研究部門に所属し、「医学と光技術を融合させた研究」を目指して、従来のバイオイメージングに加えて新しいイメージング法の開発などに従事している。
